一般的な債務整理を考えるべき目安金額
人それぞれ収入は違いますが、原則として年収の3割を超える借金を抱えている人は、債務整理の対象とみて良いと思います。300万円の年収であれば、すでに100万円以上の負債を持っている人は、リストに載っているということになります。
これは2016年6月18日に施行された改正賃金業法の総量規制によるものです。ここでは、総量規制が行われるようになった時代背景とその推移を解説しながら、借金額が年収の3割を超えた人が取るべき対策について見ていきましょう。
総量規制前の賃金業法と歴史
1980年代後半、バブル経済が崩壊し、日本は成長が止まった30年を迎えることになります。学生も卒業後に就職が困難となる就職氷河期に突入します。
こういった社会的経済不況などから、消費者金融などからの借り入れを人が増加します。
当時利息制限法を超える金利でも、出資法の上限以下であれば、高い金利(29%程度)でも貸し付けが出来たため、大手の消費社金融を中心に高金利での貸し付けが一般的でした。
そのため、返済のためにさらに他社から借りるなど多重債務者が増えていきます。
特に、督促だけでなく、違法な取り立ても横行したため、精神的にもかなり追いつめられる状況で、大きな社会問題となります。
そこで、政府は、この悪徳業者の厳罰化を含む議論を経て、2,006年12月に改正賃金法が制定されました。
この時に総量規制、つまり貸し付ける金額が年収の3分の1を超えて貸し付けてはいけないと制限されることになります。
なぜ、貸付金の制限が必要なのか?
返済能力に見合わない金額の貸し付けを行ったり、高い金利で貸し付けると、返済金額よりも金利手数料が膨れ上がります。収入の範囲では、返済が滞り、また新たに借り入れて、多重債務に陥り、自己破産するしかなくなります。
例えば、年収300万円の人が200万を借りたとします。今の金利上限は15%ですので、30日借り入れた場合、
2,000,000×0.15×30÷365=24,658円
が金利となります。これは、金利だけですので、月々の元金返済も必要です。一般的には4万~5万円ほどは返す必要があります。
対して収入はボーナスが貰えない人だと、月250,000円となりますが手取りだとおよそ187,500~212,500円程度になります。
212,500円だとしても、月40,000円の返済で、172,500円ですね。
ここから、家賃、水道光熱費、食費、保険代、その他車の維持費などが掛かれば、返済がきつくなるのは目に見えてますよね。
今の例は、1社から借りた場合で、同じ金額でも複数の金融業者から借りているとなると、金利は18%で計算されるので、返済額はもっと増加します。
例えばA社から100万、B社から70万、C社から30万の計2,000,000円借りた場合、同じ200万円ですが、利息制限法法の借入金額に対する上限金利はA社15%、B社 18%、C社18%となることから、同じ30日で借りた場合の金利は
A社:1,000,000×0.15×30÷365=12,328円
B社:700,000×0.18×30÷365=10,356円
C社:300,000×0.18×30÷365=4,438円
合計:27,122円となり、2,464円も多く金利に差が出て、その分支払いも大変になります。
以上から、年収の3割を超える借金は、支払いがきつくなるので、おすすめできない訳です。
債務整理を考えるべき人
年収の3割を越える借金をしている方や以下に該当する方は、速やかに、弁護士や司法書士(以下弁護士等という)に相談することをお勧めします。
複数の金融機関から借り入れがあり、毎月の返済が遅れている人
リボ払いを多用している人やリボ払い額での支払いがきつい人
収入がリストラなどにより低下し、回復の見込みがない人
年収の3割以上の借金をしている人が取るべき行動
任意整理には、債務者(お金を借りている人)の事情により、弁護士等が判断してくれますので、先ずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。
任意整理、個人再生、特定調停、自己破産などがあります。
相談が遅れるほど、借金額の増加、督促などの取り立てなどに悩み、仕事も手につかず、精神的にも追い詰められてしまいます。
お金がないのに、相談する金もないと思われるでしょうが、弁護士等が金融機関と交渉して、支払い計画に道筋をつけてくれますし、その中から、弁護士費用も捻出が出来ます。
弁護士への敷居が高ければ、先ずは周りの信頼できる知人に相談して、一人で抱え込むことがないようにしましょう。
【参考図書】
「99.9%解決できる!借金問題解決法}神坪浩喜著、星雲社
「いちからでなおし 自己破産」吉田杉明著、明日香出版社




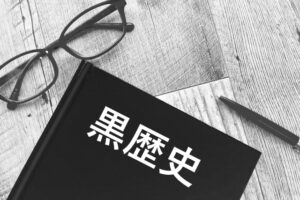




コメント